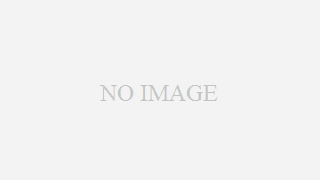 未分類
未分類 隣国との和解によって、日本は将来の戦略の選択肢を広げることができる。
新聞から米外交問題評議会上級研究員 シーラ・スミスさん海外の日本ウォッチャーにとって理解が難しいのは、なぜ消費税引き上げの先送りのために解散をしなければならないのか、です。自民党は公明党と合わせて3分の2以上の議席を持っていたわけですから、...
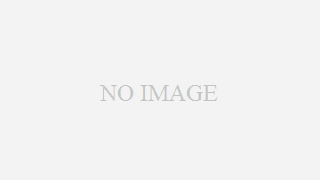 未分類
未分類 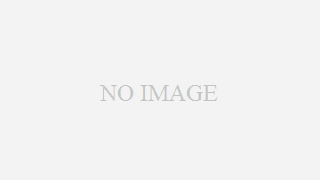 未分類
未分類 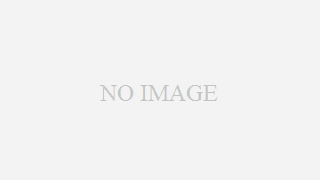 未分類
未分類 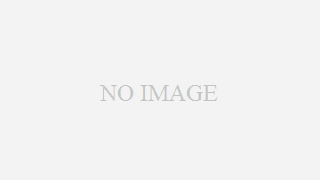 未分類
未分類 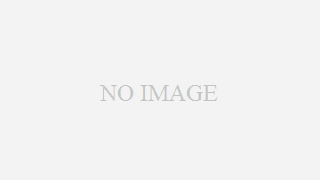 未分類
未分類 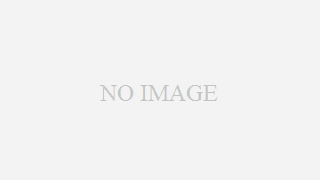 未分類
未分類 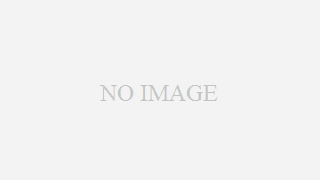 未分類
未分類 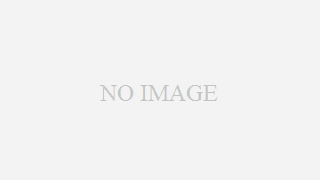 未分類
未分類 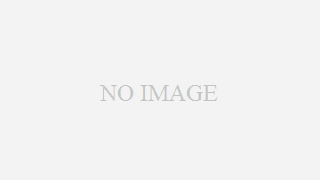 未分類
未分類 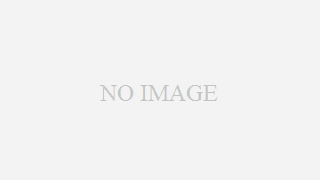 未分類
未分類